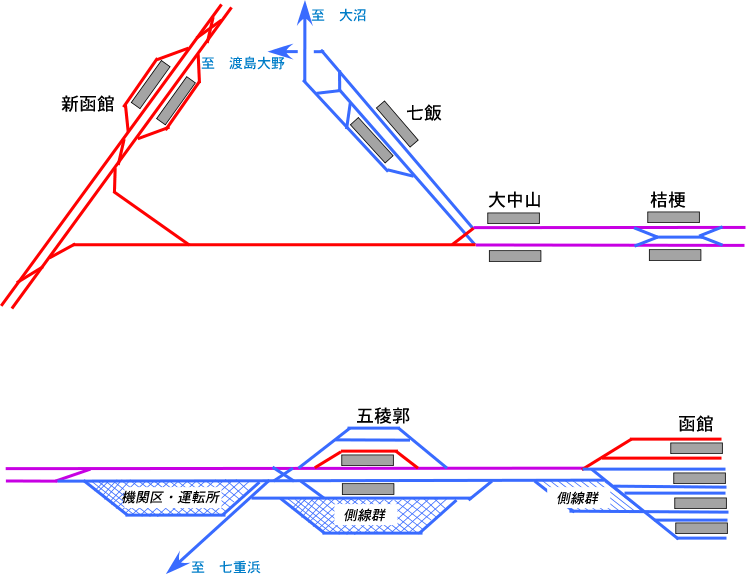新幹線函館市街乗り入れ ー 諦めるのは早い
「フル規格」にびっくり
当HPで、北海道新幹線の現函館駅乗り入れを主張してからまもなく、北海道新聞が「北海道交通研究会の研究部会」による試算として、『フル規格で現駅乗り入れなら1000億円、ミニ新幹線でも150〜250億円もの投資が必要』と報じた(2/15/2005)。「北海道交通研究会の研究部会」の真意は分からないまま、記事の論調としては『乗り入れ不可能』なのであるが、ちょっと待って欲しい。そもそも新函館〜函館間に『フル規格』など、あまりにも突拍子もない案である。この記事(Web版)の見出しが『フル規格で1000億円』とあるため、不可能が強調される形になっているが、そんな無理を前面に出すことによって、『現駅乗り入れ不可能』という印象付けを狙っているのではないか、と邪推の一つもしたくなる。ミニ新幹線にしても、わずか18kmの距離にこの試算額は大きすぎるのではないか?山形新幹線・福島ー山形間(87.1km)の地上工事費は357億円、秋田新幹線・盛岡ー秋田間(127.3km)では607億円であった。いずれも峠越えの急峻な地形を縫う線区であり、改良すべきトンネルも数多く、また単線区間が介在していたため、部分複線化が必要であった。また多くの駅での配線変更も伴った。新函館〜函館間の条件がそれほど悪いと思えない。せいぜい100億円というところであろうか。
知恵をしぼれ
新函館〜函館間の在来線線形は、山形・秋田新幹線と比較して、「極めて良好」である。在来線に標準軌を併設することは、必ずしもミニ新幹線車両だけの乗り入れを意味しない。25m長のフル規格車両乗り入れも、工夫次第では可能である。この際、現函館駅ではホームがフル規格車両にぶつかるため、在来線用とフル規格用の乗り場を分ける必要が生じるが、あの広い構内にそのくらいの余裕はあろう。中間駅ホームも同様に問題となるが、現在、在来線普通列車の編成は、ホーム有効長と比較して短いうえ列車本数も限られているため、在来線ホーム部軌道を新たに併用軌道から分岐させる形で別に設ければ解決できる。或いは、ホームがフル規格車両にぶつからないよう削り、現行のミニ新幹線車両と同じく、在来線車両側にステップを設けてしまうことで対応することもできる。平均片道1時間に1本しかない短い編成の普通気動車しか走らないため、車両の改造はさほど大がかりなことにはならない。
ミニ新幹線でもいい
鉄道以外の構造物(陸橋)などが支障して、どうしてもフル規格車両が乗り入れできないという場合は、ミニ新幹線でも構わないではないか。現在、『白鳥』などが、1日に9往復ほど運転されている。新幹線開業により、乗客が仮に倍増したとしても、E3系(ミニ新幹線車両=秋田新幹線などに使用)6両編成を、1時間に片道1本程運転すれば、十分賄える。新青森、或いは盛岡で、E2系(フル規格車両)と分割・併合して、東京まで乗り入れることとする。時速360キロの営業運転をめざしてJR東日本が開発中の新系列高速試験車も、現在のE2系+E3系と同じく、セットで使用することを前提にしているのだ。そして、本州と札幌を直通する列車は新函館に停車し、現駅には乗り入れない代わりに、現函館駅乗り入れミニ新幹線と相互連絡をすることにより、乗り継ぎの便を図る。新函館駅を図のような配線にしておけば、いろいろな使い方が可能である。新函館駅で必ず各方面列車が離合することにすれば、結果として新函館〜函館間でのすれ違い回数が減るため、図中では三線軌部分を含めかなり長く取ってある標準軌間部分を短縮し、工費を節約することも可能である。五稜郭駅には、是非ともミニ新幹線を停車させたい。
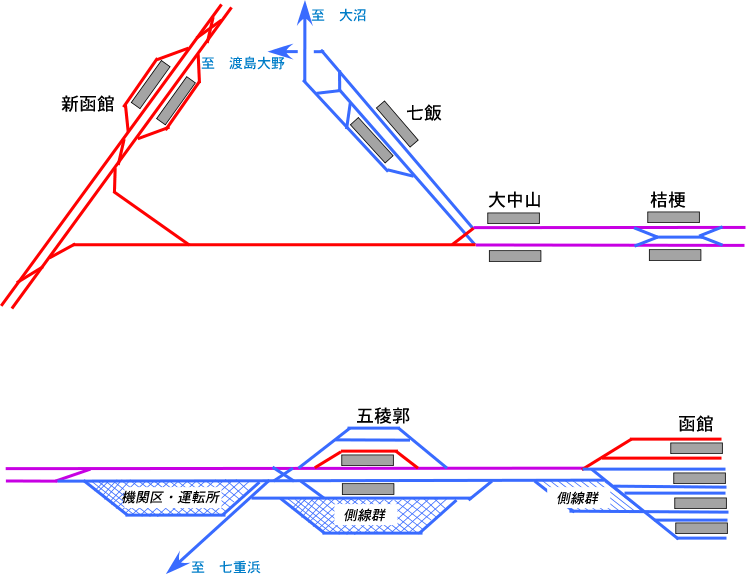
現函館へのミニ新幹線乗り入れの為の各駅配線案
赤:標準軌道、青:狭軌、紫:三線軌。
側線群は省略してある。藤代線・砂原線が分岐する七飯駅の配線を複雑にせず、かつもっとも在来線に近い場所にアプローチ線を取り付けるとすれば大中山〜七飯間となる。アプローチ線の延長はやや長く、2km程となる。沿線の大半は水田である。
現在、大中山駅は単純相対式2面2線であり、桔梗駅も同じだが、後者には撤去された中線がある。貨物列車待ち合わせのため、これを復活させている。五稜郭駅・函館駅には、側線が数多く、使用されていない部分も少なくないと考えられる。五稜郭の運転所や、海峡線への分岐をなるべく複雑にしないように、五稜郭以南では、標準軌は東側に設置することを基本とする。
|
航空を打ち負かさなければ意味がない
繰り返すが、現駅乗り入れを重視するのは、『飛行機よりも便利にしたい』からである。鉄道斜陽論者・整備新幹線不要論者が決して認識していない、或いは軽視しているのが、航空輸送のエネルギー効率の悪さ・環境に与える悪影響の大きさと、鉄道の圧倒的な環境優位性である。折角の巨費を投じて得るものが、結果として『環境負荷の低減』になるために、現函館駅乗り入れはどうしても必要である。
北海道開発予算を建設費に
ミニ新幹線函館乗り入れ改良、及び新函館以北の新幹線本体工事には、北海道開発予算を充当したい。実はこの案は珍しいものではなく、かねてから根強い意見なのだが、道東出身議員を中心に、道開発予算で新幹線を建設することに強い反対があるという。『道開発費は新幹線沿線のものだけではない』というのが理由らしいが、これはおかしい。「沿線の利益は、道全体の利益」であると、どうして考えられないのか。受益人口に応じてではなく、面積に対して均等に投じるのでなければダメだ、というのでは、多大な無駄を産む。毎年8000億円程の道開発予算(1兆円を越えていた年次もある)が、一体どう使われたのか、津軽海峡の南側から見ていても全く判然としないのは、そんな不可解な使われ方のためであろうか?この巨額の道開発予算の、毎年わずか5%でも新幹線建設に投じられていたならば、今頃とっくに新幹線は札幌まで到達していただろう。この程度の額をどうして割こうとしないのか?
「道民でもないよそ者が余計なことを言うな」という反論は、いっさい受け入れられない。道開発費には国費も投入されており、私も納税者の一人として、道開発費の使い道に口を差し挟む正当な権利を有するからだ。おかしいのは、北海道新幹線が建設されることではない。硬直化した歳出のせいで、「道民の悲願」の為なのに、本来あるはずの予算が新幹線建設費に回らず、あたかも『新幹線の建設費だけが捻出できない』ように見えることである。
←戻る